東出昌大のYouTubeがきっかけでじゃがいもに興味
東出昌大氏のYouTubeチャンネルを初めて知ったのは、SNSで話題に上っているのを見かけたことがきっかけです。
北関東の山奥に移住し、半自給自足の生活を送りながら狩猟や料理を行う様子が動画に収められており、その自然体な姿に癒しと興味を感じました。
2024年2月に初投稿がされて以降、チャンネル登録者数が66万人を超える人気を集め、自然の中での暮らしや獲物を調理する様子が多くの視聴者に支持されていました。しかし、2025年2月28日に東出氏が「3月末をもって一時休止する」と発表され、その理由として「撮影が楽しくなくなったこと」や「自身の暮らしを外部に発信する気持ちの変化」を挙げておられ、少し寂しい気持ちになりました。3月31日が最終日とのことですので、最後の配信がどのようなものになるのか気になっています。
明日の『鹿汁』回はいつもの猟師飯。
明後日の『野営』と『単独猟』回は今冬に熊を探して山をうろついていた頃の動画です。
ということで、30日『鹿汁』31日『野営』と『単独猟』になるようです。
じゃがいもが大航海時代の壊血病予防に役立った歴史
YouTubeの動画の中で、じゃがいもに関する話題が特に印象に残りました。
東出氏が料理をしながら「じゃがいもはビタミンが豊富で、大航海時代に壊血病予防に役立った」とお話しされていた記憶があり(どの動画だったかは定かではありませんが)、その一言が気になり、詳しく調べてみることにしました。
すると、じゃがいもが大航海時代に壊血病予防に貢献したという話は事実でした。
壊血病はビタミンC不足により歯茎から出血したり死に至ったりする病気で、15~18世紀の長期間航海に従事する船員たちを悩ませていました。
じゃがいもは南米原産で、16世紀にヨーロッパに伝わり、100gあたり20~30mgのビタミンCを含んでいます。保存性にも優れているため、18世紀以降、船に積まれるようになりました。船員たちはじゃがいもを茹でたり、スープにしたりして摂取していたようです。
茹でることでビタミンCは多少減少しますが、それでも壊血病を防ぐには十分な効果がありました。
ただし、18世紀末にイギリス海軍がレモンやライム(100gあたり約50mgのビタミンC)を正式に採用してからは、じゃがいもは補助的な役割を担うことが多かったようです。
船上でスープにして摂取する姿を想像すると、実用的かつ温かみのある食事だったのではないかと感じます。
じゃがいもがヨーロッパで「邪道」と嫌われた理由
一方で、じゃがいもがヨーロッパで当初嫌われていたという歴史も興味深いものでした。
16世紀にスペイン経由で伝わった際、そのゴツゴツした外見や、ナス科で毒性のあるベラドンナに似ていることから「食用に適さない」と警戒されました。
また、聖書に登場しない植物であるため「邪道である」と宗教的な理由で避けられた時期もあったようです。
「受粉せずに育つことが邪道とされた」という具体的な言及が当時あったかは不明ですが、種芋による無性生殖が当時の人々には異質に映った可能性はあります。
18世紀になり、飢饉や戦争で食糧難が深刻化すると、「邪道であっても食べられるなら」と受け入れられ、アイルランドでは主食となるまでに至りました。
北方民族の知恵:アザラシ発酵食品でビタミン不足解消
じゃがいもの話題から、さらに北方の食文化にも関心が広がりました。
イヌイットなどの北方民族が、アザラシを発酵させてビタミン不足を補っていたことを知り、驚きました。
アザラシの肉や内臓を皮に詰めて発酵させた「イグナック」や、鳥を詰めて発酵させた「キビヤック」は、ビタミンCを含むため壊血病予防に役立っていたとされています。
野菜が育たない寒冷地で、動物由来の発酵食品により栄養を確保する知恵は驚異的です。
そこで、大航海時代に発酵食品でビタミン不足を解消した事例がないか調べたところ、探検家ジェームズ・クックが1770年代にザウアークラウト(発酵キャベツ)を用いていたことが分かりました。
ザウアークラウトはビタミンCを保持するため、クックはこれにより航海中の壊血病による死者をゼロに抑えたと記録されています。
レモンほどの効果はなかったものの、発酵食品が船員の命を支えた例が存在するのですね。イヌイットとクックの事例は時代も地域も異なりますが、発酵という共通の知恵が興味深いと感じました。
トウモロコシとニシュタマリゼーション:同時期に伝わったもう一つの作物
さらに、同時期にトウモロコシがヨーロッパに伝わったと知り、そちらも調べてみました。
トウモロコシは1492年にクリストファー・コロンブスが中米から持ち帰り、16世紀初頭にスペインで栽培が始まりました。
じゃがいもと異なり比較的受け入れられやすかったものの、ビタミンCはほぼ含まれておらず、壊血病予防には寄与しませんでした。
むしろ、ナイアシン(ビタミンB3)が吸収しにくい形で含まれているため、ヨーロッパではペラグラ(ナイアシン欠乏症)が問題となりました。
一方、アメリカ先住民は「ニシュタマリゼーション」という石灰水で処理する技術を用いており、これによりナイアシンを吸収しやすくしていました。
この手法は、トウモロコシを煮て浸け、粉にする過程で偶然灰を使用したことが起源と考えられ、「宇宙人に教えられたのでは」と冗談めかす人もいるほどです。
現代のマサやトルティーヤに繋がるこの技術は、栄養を補う知恵の結晶と言えるでしょう。
現代のじゃがいも:マックポテトとコロッケの栄養価を検証
再びじゃがいもに戻り、現代の視点でも考えてみました。
「マクドナルドのポテトは野菜だ」という笑い話がありますが、栄養面はどうなのでしょうか。
フライにするとビタミンCは100gあたり10~15mg程度残り、カリウムも摂取できますので、「全く栄養がない」とは言えません。
しかし、油で揚げることでカロリーと脂肪が増え、野菜としての健康イメージからは離れてしまいます。
コロッケも同様で、じゃがいもにひき肉や玉ねぎを加えて揚げるため、ビタミンCやカリウムはある程度残りますが、油とパン粉により満足感が優先されがちです。
個人的にコロッケが好きなので栄養があると嬉しいのですが、「あるにはあるが、健康食品とは言い難い」という結論に至りました。
東出昌大から広がった食材ワールド
東出さんのYouTubeの一言から、じゃがいも、トウモロコシ、発酵食品、コロッケまで広がり、歴史と食の繋がりに感動しました。野営回大好きなので、最終日の動画楽しみたいと思います!!


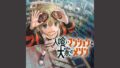
コメント